Twitterの閲覧制限が起きた理由|今後のビジネスへの影響は?
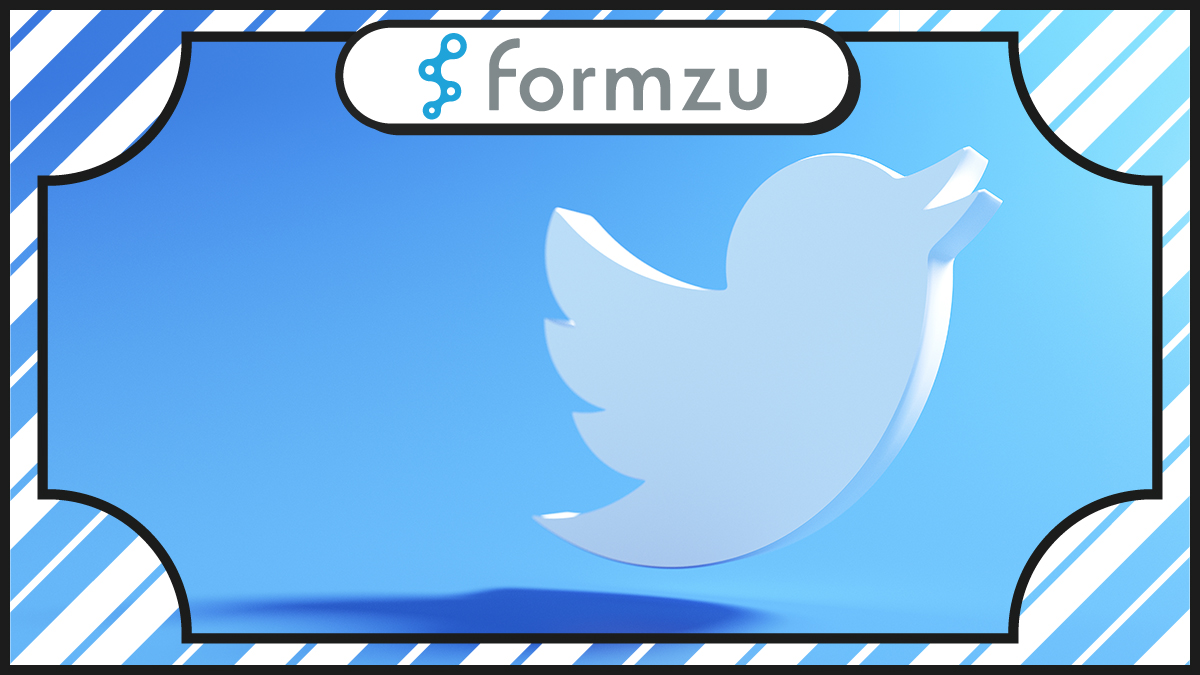
日本時間の7月1日夜、突然多くのTwitterユーザーに『API呼び出しの回数制限を超えました』という文言が表示され、タイムラインの更新・閲覧ができない状態となりました。 Twitterを運営するX corp.の代表であるイーロン・マスク氏のツイートから、閲覧制限が掛けられている現状が確認されています。閲覧制限の経緯や内容の説明、今後のビジネスへの影響などについて考察します。
この記事の目次
Twitterで起きた大規模な変化
Twitter社は2022年にイーロン・マスク氏によって買収され、彼の運営するX Corp.に吸収合併されました。
今回、閲覧上限が突然設けられた理由として、イーロン・マスク氏は自身のTwitterで以下のように発表しています。

「閲覧上限を設けた理由は、みんなTwitter中毒で外に出る必要があるからだ」ということのようです。
また、別の理由として、AIが人間の言語を学習するためのデータスクレイピングによって、一般のユーザーに対して過度な負荷がかかっていたことを挙げています。
一方、Twitter社買収の際に大量の人員整理をしたこともすでに周知の事実となっており、その際にエンジニアを解雇したことによって、今回のようなトラブルが発生したのではないかとも考えられています。
いずれにせよ、現時点(2023年7月3日現在)では、Twitterの閲覧上限が撤廃される見込みについての公表はありません。
今後は、サーバー強化、もしくは何らかのスクレイピング対策ができた時点で、再び閲覧上限数が無制限になるのではないかと推測されています。
閲覧上限はどのように変化したか
| 以前 | 制限直後 | 現在(7/3時点) | |
|---|---|---|---|
| 非登録ユーザー | 上限なし | 0件(閲覧不能) | 0件(閲覧不能) |
| 新規登録ユーザー | 上限なし | 300件/日 | 500件/日 |
| 登録・未認証ユーザー(青バッチ無) | 上限なし | 600件/日 | 1,000件/日 |
| 登録・認証ユーザー(青バッチ有) | 上限なし | 6,000件/日 | 10,000件/日 |
Twitterの閲覧上限数は、Twitterにアカウントを登録しているか、認証済みかどうかで変化します。
認証とは、政府や企業などの公的な団体、個人ユーザーが購入できるTwitter Blueという登録サービスです。

個人の場合は年額10,280円、組織の場合は月額135,000円の登録料に加え1アカウント当たり6,000円が加算されて請求されます。
認証を受けたアカウントには、アカウント名の後ろに下図の認証マーク(青バッチ)が付きます。

API制限が始まった直後は最大でも6,000件だったのに対し、現在(7月3日時点)では10,000件まで閲覧上限が増えています。
しかし、Twitterのヘビーユーザーの中には、ずっとタイムラインを流しっぱなしにしているような使い方をしている人もいます。
フォロー人数が1,000人の場合、それぞれのフォロワーが10回ずつつぶやくと、Twitter Blue認証ユーザーであっても、それだけで上限に達してしまいます。
また、Twitterは多くのユーザーが無課金の登録・未認証ユーザーです。
1日1,000件しかツイートが見られない状態は、これまで無尽蔵に流れる情報を閲覧できていたSNSユーザーからすれば不満に感じることでしょう。
今後のビジネスで考えられる影響は?
Twitterをビジネスツールとして使用している企業や個人事業主は少なくありません。
しかし、今回のAPI呼び出しの上限設定によって、これまでのSNS戦略は大きな転換を要求される可能性があります。
Twitterユーザーの流出
最も懸念されるのは、宣伝対象となる顧客、つまりTwitterユーザーの流出です。
現に、7月2日の時点で『Twitterサ終』(サ終=サービス終了)が日本語のトレンドワードとしてランクインしたり、Twitter以外のSNSへのアクセスや新規登録が集中してサーバーダウンを起こしたりと、ユーザーがTwitterから加速度的に離れていく現象が見られました。
もちろん、早い段階でAPIの呼び出し制限が解除されれば、ユーザー流出は一時的なものに留まり、TwitterのSNSとしての強さは維持されるでしょう。
しかし、この規制が長く続くと、ユーザーが流出先のSNSに定着してしまいます。
そうなれば、もしAPI制限が撤廃されたとしても、戻ってくるユーザーは一部に限定されてしまうと考えられます。
SNSは利用人口が多いほど盛り上がりやすい傾向にあるので、利用者が減少したSNSでは面白みが減り、さらなる過疎化を招くかもしれません。
Twitterを利用したプロモーションの減少
こうしたことがきっかけで、Twitterを利用した広告宣伝の費用対効果が悪化し、ビジネスツールとしての活用機会が減少していく恐れがあります。
Twitter Blueの導入など、イーロン・マスク氏が買収した後のTwitterは資本的な面を強化しつつあっただけに、広告宣伝収入が減少することで、収支の悪化が予測されます。
その結果、広告掲載料が上がったり、ユーザーに課金をさせるようなシステムの強化が行われたりして、ますます広告の減少・ユーザー離れが起きる可能性が考えられます。
また、Twitterのような巨大SNSがこのまま衰退していけば、現在は各種サービスのログイン機能としてTwitterアカウントを連携させているサービスも、次第に各サービス側から登録アカウントの変更・追加の指示が入る可能性も否定できません。
Twitterによる広告宣伝の規模縮小
最終的にTwitterのタイムラインには、『ツイ廃』と呼ばれるごく一部のヘビーユーザーの人たちのつぶやきと、彼らのみをターゲット層に絞り切った広告のみが展開されるようになるかもしれません。
このような未来を迎えた場合、広告を行う事業者としてはTwitter以外にもオンライン上で広告を出せる場所はありますし、「わざわざ利用者が少なくて投資費用の高いTwitterで行う必要はない」と判断することになるでしょう。
こうした顧客流出、サービスの形骸化・終了という変化は、従来であればすぐには訪れないものでした。しかし、情報化社会の進化によって、人々がより新しいものに飛びつきやすくなっている現代であれば、Twitterは想像よりもずっと早く廃れてしまう可能性があります。
閲覧上限は撤廃されるか?
Twitterがこうしたリスクを回避するためには、なるべく早い段階で閲覧上限を撤廃することが求められるでしょう。
もちろん、X corp.やイーロン・マスク氏も、将来的にはいずれかのタイミングでAPI呼び出し制限を撤廃するつもりでいると考えられます。
しかしながら、設備の増強やシステムの再構築などを行っているのであれば、この事態を一瞬で解決することは難しいかもしれません。
SNSをビジネスツールとして利用する事業者であれば、Twitter以外のSNSや新たな媒体にどのようにユーザーが流出していくのかについても、目を光らせておく必要があるでしょう。
『ポストTwitter』となるSNSの候補は
Twitterからユーザーの流出が続いた場合、次に最大手となる可能性があるSNSはどのようなものがあるか、紹介します。
以前からユーザー数の多い、画像や写真の共有をメインとしたSNS。Twitterとはユーザー層が異なるとされていたが、流入・流出により変化が起こる可能性がある。
Instagram公式サイトへのリンク
Mastodon
脱中央集権的、非商用をテーマにしたSNS。広告の表示はないが、企業がPR活動として自社広報のアカウントを持つことは制限されていない。
Mastodon公式サイトへのリンク
Misskey
分散型マイクロブログSNS。『レターパックで現金送れ』『与謝野晶子』など、Misskey内でしか伝わらない独自の文化が構築されつつあり、2010年代のTwitterのような雰囲気という意見もある。
Misskey公式サイトへのリンク
blue sky
2019年にTwitterから独立した部門が開発しているSNS。「昔のTwitterを目指している」ということだが、現在はβ版までしか展開されていない。新規登録についても待機リストへの登録にとどまっている。
blue sky公式サイトへのリンク
くるっぷ
イラストや小説などの創作に特化したSNS。特定の層に特化した形式のSNSであるため広告宣伝の効果もある程度限定されるが、ユーザー層と合致すれば高い効果が期待できるかもしれない。
くるっぷ公式サイトへのリンク

Instagram以外は「現行のTwitterでは物足りないユーザーに向けて開発を進めてきた」雰囲気があり、今すぐにどこかのユーザーが爆発的に増えて構図が変化する、とはならないかもしれません。
しかし、ユーザーの新規流入によってSNS自体の雰囲気が変化する可能性もあります。
これらのSNSがどう変化していくかも、気にしておくといいでしょう。
今後の広告宣伝戦略を見直すチャンスかも
近年のSNSを利用した広告戦略では、Twitterは非常に強力でした。
また、ビジネスツールとしての側面も非常に優れていました。
しかしながら、今回のTwitterのAPI呼び出し上限『騒動』によって、ユーザーの動向が大きく変わる可能性があります。
Twitterにとって代わる新しいSNSがあるならば、そこでの広告宣伝を検討していく必要もあるでしょう。
これまでうまくTwitterで広告活動をできていなかった企業も、B to Cにおける広告宣伝を見直すチャンスかもしれません。



