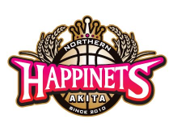プレゼン資料を見やすく!伝わるデザインやおすすめのツールも紹介
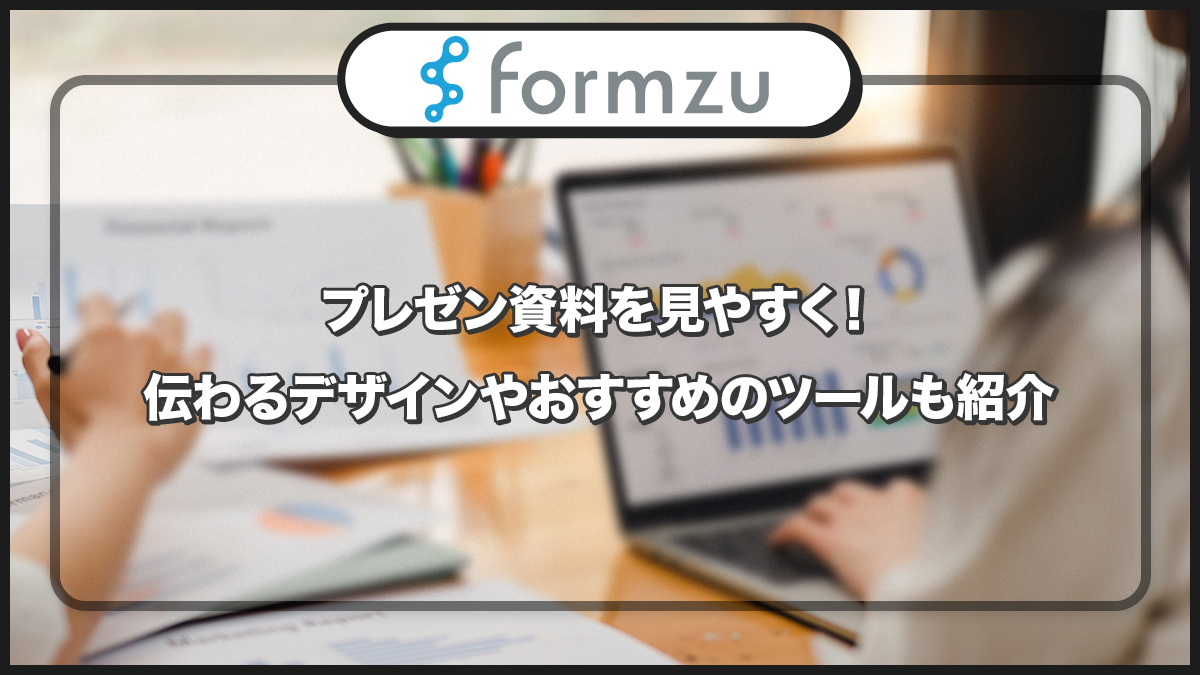
ビジネスの場で欠かせない「プレゼンテーション」。どんなに内容が優れていても、資料が見づらい・伝わりにくいと、聞き手の印象や理解度は大きく下がってしまいます。逆に、構成とデザインを少し工夫するだけで「伝わる」「印象に残る」プレゼンに変えることができます。
この記事では、誰でもすぐ実践できる見やすい資料作りのコツと、取り入れやすいおすすめのツールをご紹介します。
この記事の目次
資料の目的を明確にする
最初に大切なのは、「何を伝えるための資料か」を明確にすることです。プレゼン資料には大きく分けて3つの目的があります。
説明型(社内報告・提案など)
→ 理解を促す構成・データの正確さが重要
説得型(営業・プレゼン大会など)
→ 感情に訴えるビジュアルやストーリーが効果的
共有型(会議や教育用)
→ 要点整理と視認性がポイント
目的に応じて、情報量・トーン・デザインの方向性を変えることが、伝わる資料作りの第一歩です。

見やすいレイアウトの基本ルール
視覚的に整理された資料は、理解されやすく、印象に残りやすいです。ここでは、すぐに実践できる5つの基本ルールを紹介します。
1スライドに1メッセージ
1枚のスライドに伝える内容は1つだけに絞りましょう。複数の情報を詰め込むと、聞き手の注意が分散してしまいます。
例:「課題」「原因」「解決策」はそれぞれ別スライドに。
余白をあける
白いスペース(余白)は「見やすさ」の味方です。
ぎっしり詰まった資料よりも、余白を活かしたレイアウトの方が読みやすく、洗練された印象になります。
文字サイズは「発表距離」を意識
遠くからでも読めるように、タイトルは30pt以上、本文は20pt以上が目安です。
特にオンライン発表では、画面共有でも見やすいフォントサイズが重要です。
色は3色以内にまとめる
カラーパレットは「ベース色」「アクセント色」「強調色」の3色を基本にしましょう。
背景と文字のコントラスト(明暗差)を意識して、可読性を保ちましょう。白背景×黒文字×青アクセントなど、シンプルな配色が◎。
図解で理解を助ける
長文で説明するより、図やアイコンで視覚的に伝える方が早く理解されます。
たとえば、プロセス説明ならフローチャート、比較なら表やグラフを使うと効果的です。

デザインの質を上げるポイント
フォントの統一
フォントがスライドごとに違うと、全体が雑多な印象になります。
資料全体で「1〜2種類のフォント」に統一しましょう。
例)
タイトル:ゴシック系(メイリオ、Noto Sansなど)
本文:明朝系(游明朝、Noto Serifなど)
アイコン・写真の活用
視覚的な情報は印象に残りやすく、感情を動かす効果があります。
無料素材サイト(例:いらすとや、ICOOON MONOなど)を活用すると便利です。
図表を「見やすく」加工
グラフをそのまま貼るよりも、重要な部分を強調色で目立たせると効果的です。
たとえば、棒グラフの1本だけを赤くして「ここがポイント」と示すなど。

効率よくデザインできる!おすすめツール
ここからは、おすすめのプレゼン資料作成ツールを紹介します。
Canva(キャンバ)
- 特徴:直感的な操作で、テンプレートが豊富。
- おすすめポイント:日本語フォントも多く、ビジネス用途のテンプレートも充実。
- 用途:デザイン初心者でも「プロっぽい」資料を短時間で作成可能。プレゼン資料だけでなく、SNSの投稿デザインの制作にも利用可能。
イルシル
- 特徴:3,000種類以上のテンプレートを備え、入力したテキストやキーワードからスライド構成+デザインを自動生成。
- おすすめポイント:スライド作成に慣れていない人でも、短時間で見栄えの良いスライドを作成可能。テンプレート数が豊富なので、用途に応じて選びやすい
- 用途:個人・中小チームでの提案資料、社内報告、企画書、プレゼン準備。
MiriCanvas(ミリキャンバス)
- 特徴:無料プランでも50,000個以上のテンプレートを利用可能。ドラッグ&ドロップ式の直感的UIで初心者でも扱いやすい編集画面。
- おすすめポイント:文章や画像の生成を自動で提案してくれるため、素材探しや言葉選びの手間を省ける。
- 用途:資料・ポスター・バナー・SNS投稿など、さまざまな形式のビジュアル制作。
Visme(ビズミー)
- 特徴:データ可視化に強い。グラフやインフォグラフィックが簡単。
- おすすめポイント:プレゼン+レポート+動画など、多様なアウトプットに対応。
- 用途:データや情報をグラフ・図表・アニメーションでわかりやすく表現できる。
効果的に伝えるプレゼンのコツ
スライドに書きすぎない
スライドは「読む」ものではなく「聞かせる」もの。
文章を削ぎ落とし、キーワード中心で構成しましょう。
ストーリー性を意識する
「問題 → 解決策 → 効果 → 結論」という流れ(起承転結)を意識すると、聞き手が内容を追いやすくなります。
アニメーションや効果を最小限に
派手なアニメーションはかえって集中を妨げます。
「フェード」「出現」程度のシンプルな演出に留めましょう。

まとめ:伝わる資料は「デザイン×目的意識」で決まる
プレゼン資料を「見やすく・伝わる」ものにするためには、単にデザインを整えるだけでなく、「何を、誰に、どう伝えるか」を明確にすることが大切です。
- 1スライド1メッセージ
- 余白・フォント・配色を統一
- 図解とビジュアルで直感的に伝える
- ツールを活用して効率よくデザインする
これらを意識すれば、聞き手の印象に残る「プロフェッショナルなプレゼン資料」を作ることができます。